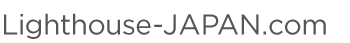2016
第2海堡灯台 DAINIKAIHO
35 18.7 N 139 44.5 E
M6368 Daini Kaiho. Fort No 2
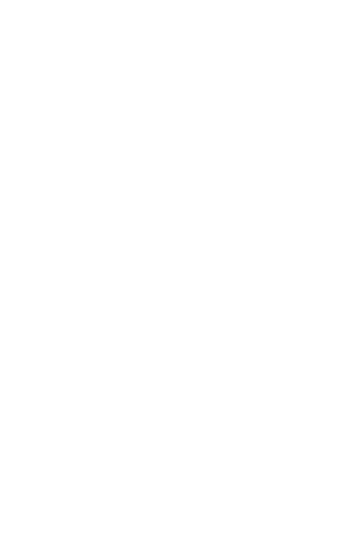
| 塗色構造 | 白塔形 |
| 灯 質 | 単閃白光 |
| 毎5秒に1閃光 | |
| Fl W R 5s | |
| (赤光は分孤) | |
| 光達距離 | 13海里 |
| 塔 高 | 12メートル |
| 灯 高 | 20メートル |
| 初 点 灯 | 明治27年9月 |
第2海堡灯台は東京湾の中央部にある軍事要塞として明治時代末期~大正時代につくられた第2海堡にあります。海保は純国産の人工島で終戦時には連合軍により破壊されたそうで当時の面影はありません。
毎度々になりますが今回も東海汽船「さるびあ丸」の甲板から撮影しました。背景にスカイツリーが確認できます。
2020/03/20
アクセス
★☆☆☆☆
地図
平成31年(令和元年)より旅行会社から上陸ツアーが開始され上陸できるようになりました。
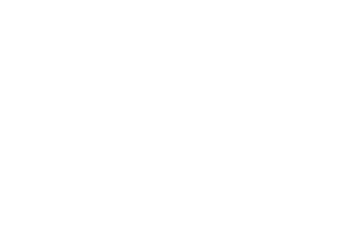
第二海堡の南側から見た全体像。灯台が目立ちます。ソーラーパネルが右側に並んでいる。
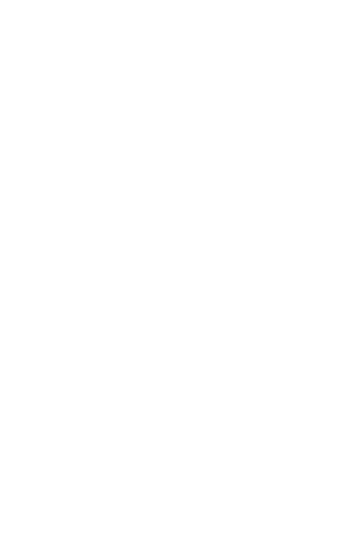
第2海堡灯台は前回上陸しましたが今回は東海汽船の上からの撮影です。八丈島からの帰りに撮った画像とほとんど変わりませんが灯台周辺の柵が無くなっているので掲載することにしました。
灯台はFRP製の塔体に回転式のフレネルレンズを備え脇にはLED灯の副灯も備えています。
東京湾の中ほどにありここから横浜港へ向かう船舶と東京港・千葉港へ向かう船舶が分かれるところでもあります。
2020/03/7
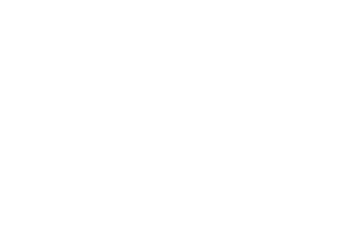
第二海堡は明治末期に作られた軍事要塞。当時の面影はありませんが夕闇に灯台が光ってる様はどことなく無機質な感じがします。
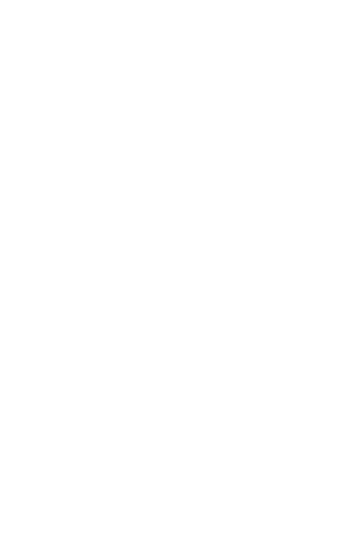
2005年(平成17年)より上陸が禁止されていた第二海堡ですが、一般人の上陸が可能なトライアルツアーが期間限定で始まりましたので行ってきました。
灯台は航行量の多い浦賀水道の真中にあり東京港への入口として重量な航路標識となっています。ただ航路自体は狭いので昼間というよりはやはり夜間の重要性の方が高そうな感じです。光源はまだフレネルレンズで光る姿は惚れ惚れします。夕暮れ時にでも観音崎あたりで見たいですね。
第二海堡自体は当時の面影は殆どなくツアー的な面白さに関しましては?でしたが、専門的知識のある人または軍事廃墟マニアの方にとっては楽しいのかもしれません。
2018/11/11
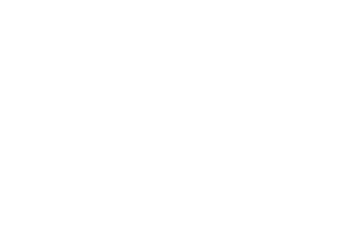
フレネルレンズ。拡大すると4面のようですので20秒で1回転なのかもしれません。左右のLED灯はおそらく副灯だと思います。このタイプは初めて見ました。
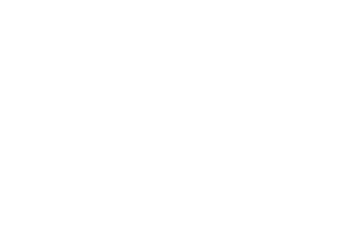
八丈島の帰りに東海汽船から見た時には周囲に囲いがありましたがこのツアーの為に撤去されたようです。
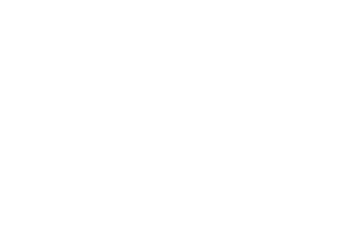
南側から。こちら側だと順光で撮れます。今日はうす曇りで青空がスカッと出なくてイマイチなコンディションでした。
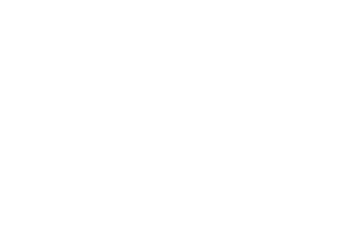
上陸前のクルーズ船より。灯台の脇にはソーラーパネルが並んでいます。
ちなみに私「だいにかいほ」だと思っていましたが「だいにかいほう」というらしいです。(ツアーパンフレットより)
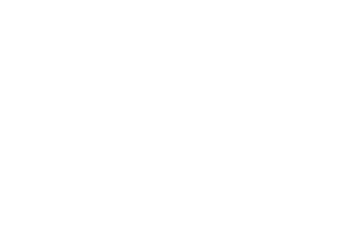
初点記念銘板
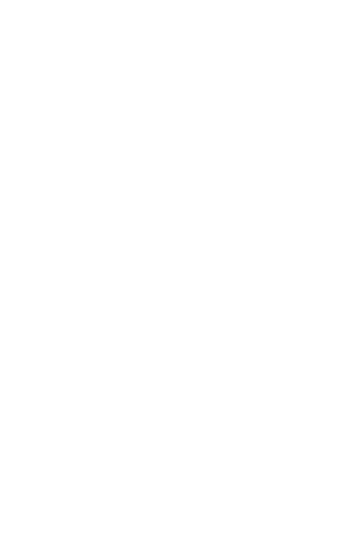
浦賀水道から東京港に入るところに大正時代位に帝都防衛の為に作られた海堡があり現在は第一、第二が残っています。その第二海堡上の灯台で残念ですが一般人の上陸は出来ません。
灯台は航路が狭くなっているところにあるので大きく光源も強い。灯台の脇には巨大なソーラパネルが並んでいます。この工事は2015年に完成されたそうなのでLEDのでも良かったかもしれませんがわざわざフレネルレンズを残したのは何か意味があるのでしょうか?
2017/3/19
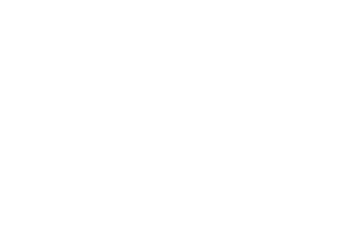
やはりフレネルレンズは光源が強く眩しく輝いていた。
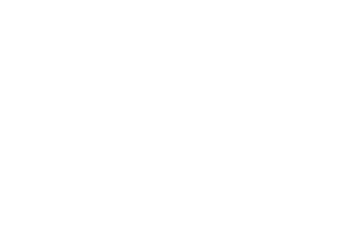
実際見たときはLBかも知れないな~と思っていましたが画像を拡大してみるとレンズでした。
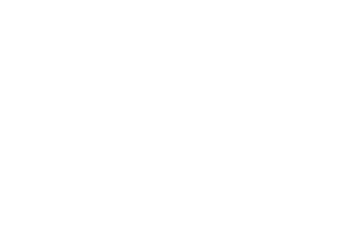
巨大な軍事要塞。上陸してみたいがよほどのコネが無ければ難しそう。
工事に次ぐ工事でもう昔の面影は無さそうです。
【沿革2016】
1894年(明治27年)09月
初点2007年(平成19年)02月13日
光度測定作業(1720~2020)航路標識測定船「つしま」(1400トン)により、灯台の光度測定作業が実施される。2010年(平成22年)03月01~4日
船舶気象通報等一時業務休止(機器改良改修工事に伴う気象情報提供一時業務休止)2015年(平成27年)03月04日
船舶気象通報一時業務休止 1000~1500(予備日9日)観測した気象情報(風向・風速)の提供が一時休止される。交換作業に伴う気象情報の提供休止2019年(令和元年)11月08日~30日
補修工事(外壁の改修工事に伴う仮設足場及び工事用シート設置)2019年(令和元年)12月25日)
船舶気象通報一時業務休止 1000~1300観測した気象情報(風向・風速)の提供が一時休止される。交換作業に伴う気象情報の提供休止※沿革は水路通報及び海上保安部WEBサイトからの二次資料であり正確を期するものではありません。
- 北海道 Hokkaido
- 青森県 Aomori
- 岩手県 Iwate
- 秋田県 Akita
- 宮城県 Miyagi
- 山形県 Yamagata
- 福島県 Fukushima
- 新潟県 Niigata
- 富山県 Toyama
- 石川県 Ishikawa
- 福井県 Fukui
- 茨城県 Ibaraki
- 千葉県 Chiba
- 東京都 Tokyo
- 神奈川県 Kanagawa
- 静岡県 Shizuoka
- 愛知県 Aichi
- 三重県 Mie
- 京都府 Kyoto
- 大阪府 Osaka
- 和歌山県 Wakayama
- 兵庫県 Hyogo
- 鳥取県 Tottori
- 岡山県 Okayama
- 島根県 Shimane
- 広島県 Hiroshima
- 山口県 Yamaguchi
- 香川県 Kagawa
- 徳島県 Tokushima
- 愛媛県 Ehime
- 高知県 Kochi
- 福岡県 Fukuoka
- 大分県 Oita
- 佐賀県 Saga
- 長崎県 Nagasaki
- 熊本県 Kumamoto
- 宮崎県 Miyazaki
- 鹿児島県 Kagoshima
- 沖縄県 Okinawa